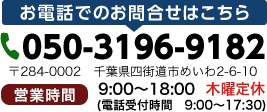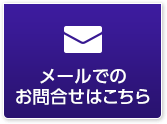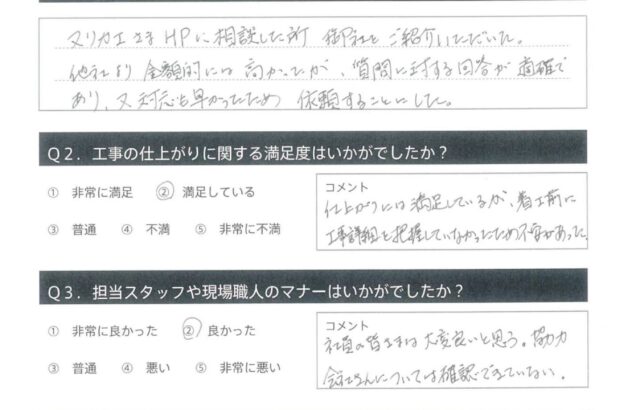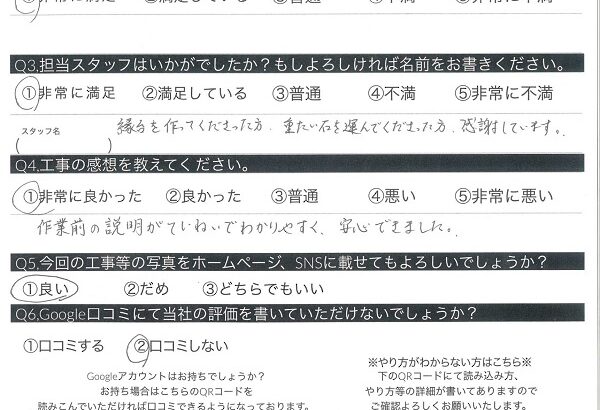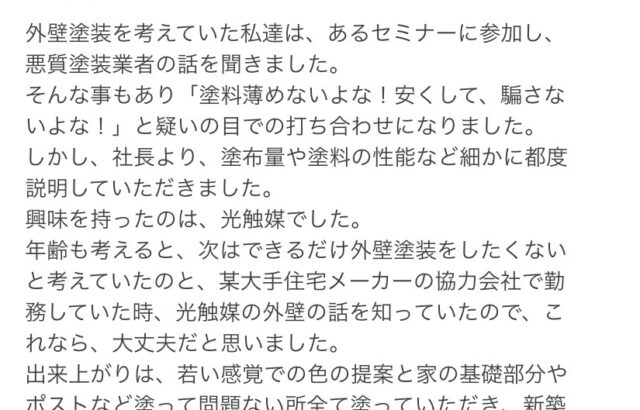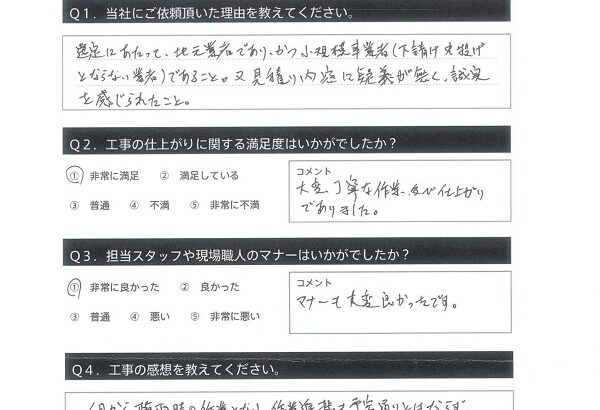棟板金の釘浮きはなぜ起こる?原因や補修しなかった場合のトラブルについて紹介
投稿日:2025.10.18 更新日:2025.10.29

住宅を紫外線や雨などから守るために設置されている屋根ですが、その中でも重要な役割を果たしているのが棟板金です。
釘で固定されている棟板金ですが、年数の経過によって生じるのが釘が浮いてくる現象です。
釘の浮きはどの住宅でも発生することですが、放置してしまうと深刻なトラブルにつながる可能性があるため、適切に対処することが大切です。
本記事では、棟板金の釘浮きが起こる原因と、補修しなかった場合に発生するトラブルについて詳しく解説します。
棟板金とは
棟板金とは、屋根の最も高い位置に設置してある棟部分を覆う板金のことです。
スレート屋根や金属屋根などに取り付けられているもので、屋根材の隙間から雨水が浸入しないように保護する重要な役割を担っています。
棟板金の下には貫板と呼ばれる下地材があり、その上から棟板金を被せて、横から釘を打って固定しています。
この釘はさまざまなことが原因となって次第に浮いてしまいます。
釘浮きの原因については次で解説します。
棟板金の釘浮きが起こる原因
棟板金の釘浮きは、以下のようなさまざまな要因によって発生します。
熱膨張と収縮
釘浮きの最も大きな原因は、温度変化による金属の熱膨張と収縮です。
棟板金は直射日光を受けやすいため、日中の暑い時には金属が膨張して、その際に釘も一緒に外側に引っ張られます。
そして、夜間の寒さで収縮しますが、この際棟板金は収縮しても釘はそのままの位置に残ったままの状態になります。
この動きを繰り返すことで釘が浮き、次第に抜けてきてしまうのです。
とくに寒暖差の激しい地域では、この現象が顕著に現れます。
貫板の経年劣化
棟板金の下地材となる貫板は木材で作られていることが多いため、雨風の影響で腐食や劣化が進んでしまいます。
貫板が腐食すると釘をしっかりと固定できなくなり、結果として釘が浮いてきてしまうのです。
とくに防水処理が不十分な場合や、湿気がこもりやすい構造の場合は劣化スピードは加速します。
さらに、棟板金そのものの劣化も釘浮きの要因です。
棟板金の耐用年数は通常15〜20年程度とされており、年月が経つにつれて釘に錆が発生したり棟板金自体が劣化したりします。
このような変化によって釘を固定する力が弱くなり、釘が浮きやすい状態になるのです。
強風による影響
台風や強風時には、棟板金が風によって浮き上がろうとする力が働き、このような力が何度も繰り返されることで、釘が徐々に抜けかけた状態になっていきます。
屋根の一番高い部分である棟板金はとくに風の影響を強く受けやすいため、釘が浮きやすくなります。
釘浮きを補修しなかった場合に起こるトラブル
棟板金の釘浮きは放っておくとさまざまなトラブルが発生するため、放置せずに補修することが大切です。
雨漏りの発生
釘浮きが起こると棟板金と貫板の間に隙間ができ、この隙間から雨水が侵入してしまいます。
また、浮いた釘の釘穴から雨水が浸入する可能性もあり、屋根材の腐食や雨漏りへとつながってしまいます。
雨水が浸入してすぐは症状としてわかりにくいですが、徐々に天井や壁のシミとして症状が現れ、最終的に室内の雨漏りが発生してしまうのです。
棟板金の飛散
釘浮きは放置すると、強風などによって次第に釘が抜けてきてしまいます。
釘が完全に抜けてしまうと、棟板金の飛散リスクが高まり、通行人に当たったりすると非常に危険です。
また、隣家に当たって窓ガラスを割ったりすることもあり、大きな事故や損害賠償責任につながる可能性もあります。
貫板や野地板の腐食
釘浮きによって雨水が侵入すると、貫板や野地板などの下地材が腐食していきます。
早期に釘の打ち直しをすれば費用は最低限で済みますが、放置して腐食が進行すると貫板の交換や野地板の補修が必要となり、修繕範囲も広がって補修費用も高額になってしまいます。
また、木材の腐食が進むとシロアリの発生リスクも高まり、建物の構造的な強度にも影響を及ぼして屋根全体の強度が低下します。
最悪の場合は、屋根の葺き替えが必要になるケースもあるため注意が必要です。
屋根葺き替え工事については「屋根の葺き替え工事って?メリットやデメリットについても解説」をご覧ください。
棟板金の釘浮きの補修について
棟板金は屋根の頂上を覆っている重要な部材で、釘浮きは雨漏りや棟板金の飛散につながるため、できる限り早めの補修が必要です。
ただし、貫板自体が腐食している場合や複数箇所で釘浮きが発生している場合は、部分補修では不十分なので、棟板金全体の交換を検討しましょう。
釘浮きを補修する際は、まず浮いている釘の状態を確認します。
そして、抜けかけている釘を撤去し、新しい釘を打ち直します。
釘を打つ際は、同じ穴に打ち直すとすぐに緩んでしまうため、元の位置よりも少しずらした位置に新しいビスや釘を打ち込みます。
また、使用するビスは錆びにくいステンレス製のものや、保持力の高い棟板金用ビスが推奨されています。
従来の鉄釘は経年劣化で錆びやすく、再度浮きが発生しやすいためです。
ビスは貫板までしっかりと届く長さのものを選び、打ち込み後、ビス頭にシーリング材を充填し、雨水の浸入を防ぎます。
まとめ
棟板金の釘浮きは熱膨張や経年劣化など、さまざまなことが原因となって発生する現象です。
釘の緩みを聞くと大した問題ではないようにも思えますが、補修をせずに放置すると雨漏りや棟板金の飛散など深刻なトラブルにつながります。
そのため、定期的な点検をおこない、釘浮きを発見した場合は早めに専門業者に相談することが重要です。
適切なメンテナンスによって安全で快適な住環境を維持することができます。
また、屋根での高所作業は転倒や転落の危険が伴うため、自分で補修しようとせずに専門業者への依頼をおこないましょう。
*K*
当社では無料診断をおこなっておりますので、「プロが見る無料診断」をぜひご利用ください。
千葉市、四街道市、佐倉市ほか、千葉県全域で、塗装工事、屋根工事のことなら、四葉建装へお気軽にご相談ください。
千葉県千葉市|外壁塗装・屋根塗装【(株)四葉建装】